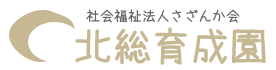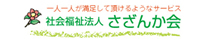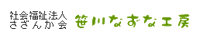2013年3月8日
北総俳壇

北総俳壇
□石渡 啓子
寒いなあ 今日の夕飯 鍋にしよ
□石橋 琴美
◎原木を 運ぶ足もと 秋の色
□吉田 祥子
青空に うろこの雲が うかんだ
□内田 沙和
トントンと なり響く音 紙工芸
□石橋 絵里
きれいだな フレームいっぱい
シクラメン
□加瀬 裕一
◎秋風に 吹かれて励む 農作業
□杉本 和彦
△海の幸 山の幸 一番は命の幸
□高木 恭一
△フタ開けて おー肉だ!と
昼ごはん
□菅谷 大輔
◎椎茸のでる数驚く 秋空の
取る顔皆誇らしげ
□信田 陽子
うだるような暑さも過ぎ
秋の澄み渡った青空と
清々しい空気の中 時折冬の気配
□安藤 悠果
◎朝けんか 今日はなんで
怒っているの?
□金子 晴奈
「おはよう」と真白い息がもくもくと 落ち葉掃きの手が止まる
□齊藤 到
△秋になり 夏の暑さも なつかしい
□米川 育美
紅葉おち 紅葉のじゅうたん
できあがり
□石上 喜章
△岩井さん 走るの案外 早かった
□絵鳩 典子
出勤し 建設事務所の 標語見る
高い意識に 背筋伸び
□白樫 久子
霜月の夜にぽっかり月明かり
家路に急ぐ 君もみてるか
□梶浦 美緒
◎止まったり 寄り道したり
戻ったり
長くて遠い 紙工への道
□興梠 孝
熟し柿 秋深まりし 北総の里
□青野 豊市
毎日が 仲間どうしの にらめっこ
□篠塚奈緒美
食べたいな食べたいな
でもないな あの柿の木
□猪田 昌宏
思い出す しだれ桜と 作業棟
□保科 智子
栄子さん 歳も縫い目も 北総一
太田さん 早く元気に 帰って来い
三浦圭織 特別枠!
・風邪ひくな! 言ってる私、 風邪っぴき
★利用者に 心配される 支援員
・らっきょう 食べられないが、作ってる(笑)
・林産班 負けてらんない 農耕班
・明けの朝 うとうと眠る 耐えられず
・小松菜と ほうれん草は わからない
・靴反対 言ってる本人 靴反対 (新島さん)
・金がない ご飯は食べず みかん食う
(今の私の状況)
・早く寝て! 言ってる自分は 夜行性
・コーヒーを 作るのだけは 自信ある
(作業後のコーヒー)
「21歳、今思うこと」
たまに、ふと「何で私はここにいるのだろう?」と考えてしまうことがあるが、北総の利用者との出来事や、仲良くしてくれる職員のことを思うと、やっぱりここにいたい!私はまだまだここにいるべきだ!と思える。就職してまだ半年しか経っていないが、この人たちに出会えて良かったと心から思えている。人生捨てたもんじゃない(笑)
選者寸評
言葉を琢く。この人たちが笑っている。泣いている。怒っている。汗流して「働くこと生きること」している。遠くを見ている。職員はその様子から心を読み取り言葉にする。近藤原理先生の「優しい言葉で深い思想を」に至る、同じに見えて同じでないこの人たちに寄り添う一期一会の坂道。「トオチャン、カアチャン、アイタイ」。毎日の暮らしの中からポロッとこぼれ落ちる真珠のような言葉。職員はこの人たち探しの旅を続ける。それらの言葉は汗臭かったり、冷たい雨の音だったりが彩りを添える。
もう20年以上もこの道を歩み続けてくれている職員の投句。中にはこの道の奥深さを知るには、少し役者不足の新職員の句。長い時間、言葉を鍛える練習をしているはずのベテランが苦戦し、駆け出しの一年生が伸び伸びとこの人たちとの暮らしを拙い言葉で活写。五七五の北総の暮らしのキャンバスが広がる。そのアンバランスが面白い。そんな中、今回の収穫は一年生職員の三浦氏。へたくそだが読む人の心をつかむ。しかも今回、一番多く投句してくれた頑張り屋。この際、彼女のコーナーを持つことにした。
「選者 虎風山人」
★最優秀賞 ◎優秀賞 △佳作
2012年7月8日
今年度もドクダミ採りご協力頂きありがとうございました

今年度も無事にドクダミ採りを終了する事ができました。収穫量としては約2トンを収穫することが出来ました。ご協力ありがとうございました。梅雨時ではありましたがうまく晴れ間にあたりドクダミ採り、乾燥と順調に行き無駄にすることなく乾燥も進める事ができました。
今年の実施日
6月30日の時点での製品化の進行状況は以下の通りです。
・袋詰めまで終わったもの(在庫と売ったのも含め)——–約70袋
・乾燥を終えたもの——–米袋105袋(製品化するとおおよそ約1650袋分)
◎今年のドクダミを全て製品化するとおおよそ約1700袋出来ます。金額にすると約50万円の売上げになります。
今年度のどくだみのまとめ及び反省
5月31日(木) 全園体制① 場所;旧山田町新里(初) 参加人数28名 天候;晴れ
今年度最初のどくだみ採り、新職員も5名参加。場所は新しく見つけた場所で丈量とも申し分なかった。70束収穫。
6月5日(火) 全園体制&吉野さんボランティア 場所;旧小見川町織畑 参加人数;19名 天候;曇
二回目の全園体制ではもう10年以上ボランティア頂いている吉野さんご夫婦も参加してとなる。場所は一昨年発見した場所。丈はもうひと伸び欲しかったが50束収穫できた。
6月4日(月)~6月16日(土) 職員ドクダミ供出期間 場所;東庄、小見川、山田など
今年職員のノルマとして常勤男子職員3㎏×3束。常勤女子職員3㎏×2束。嘱託職員3㎏×1束。
パート職員3㎏×1束もしくは一時間の無料奉仕という設定で行っている。新職員は上席職員と採りに行き、山に分け入って自然の中でできる仕事に汗を流してくれた。全体で420㎏収穫。
6月12日(火) 林産班単独 場所;旧小見川町旧本多病院跡(初) 参加人数;11名 天候;曇
翌日の明社ボランティアに備え林産班のみで採りにでている。場所はチラシを見た方が自分の土地に生えているとの情報をもらい、そこで採っている。丈はまばらではあるが供出分などで採る分には十分。
6月13日(水) 明るい社会づくり船橋市推進委員会ボランティア 場所;旧山田町新里(初)
旧小見川町織畑(初)
参加人数;34名 天候;曇
今年で北総のボランティアに来ていただいて25年以上が経つ明社の方々。農耕のらっきょうと林産ドクダミに分かれて入って頂いた。林産には17名が入って頂いた。午前が林産班で新しく見つけた場所で、午後はチラシを見た小見川地域の方がご自宅の裏山にあると教えてくださり、丈も太さも良いものが群生していた。収穫量としても180束と近年では最高に近い数字を出すことができている。
6月19日(火) 保護者ボランティア 場所;旧小見川町織畑佐久間さん山・角田さん山
参加人数;32名 天候;曇
保護者と職員合同のドクダミ採り。今年も述べ31名の保護者ボランティアを頂き、15名が林産班に入って下さった。16名は農耕班のらっきょう加工へ。採った場所は明社に続き、旧小見川町の織畑の新しい群生地と利用者角田さんの祖父の所有地で収穫している。丈もよく太さも十分のものが採れ165束採れたが、今迄の保護者ボランティアでは一番に近い収穫量があった。
6月30日(土) スリーライトボランティア 場所;旧小見川町織幡角田さん山 参加人数;18名 天候;晴
スリーライトさんのボランティアは今年で3度目。今年度は5名の方が来園され、初めての方は1名。今年も手伝いに来るのを楽しみして頂き、天候にも恵まれ、丈も十分ながく良いものが採れている。数量としても24束と束的には少ないが量としては去年とそん色ない。
まとめ
今年度のドクダミ収穫量から見ると昨年から約400kgの増。目標の1.8トンより300kg多く採る事ができました。今年に関しては春先の気候も安定し、芽吹きも例年通りで丈も太さも良いものが沢山伸びた事が要因としてあります。
毎年ドクダミボランティアを継続して下さっていたほたかの会の皆様はご高齢になり、今年度のボランティアには参加できない事をお手紙で頂戴致しました。長年のご協力ありがとうございました。保護者、船橋明社の皆さん、吉野さん、スリーライトさんのボランティアの方々にはドクダミ採りを毎年心待ちにして来て頂いています。船橋明社の皆さんにはもう今年で25年目、吉野さんも10年以上と継続して頂いており、園長が強く信頼関係を築いてこられた事に他なりません。昨年は丈の短さに苦慮しましたが、今年はどのボランティアさんも満足して採っていただけるようなドクダミ採りになったと思います。今年度の特色として園長より地域の皆様にドクダミ群生地の情報提供をお願いしたらどうかと助言があり、新聞の折り込みチラシとして香取市中心に約13000部配布。結果、有り難いことに沢山の情報を頂く事ができました。その情報提供がなければ今年はこれほど良い成果も果たせませんでした。改めて地域の力を借りて私たちの仕事が成り立つ事が実感できました。情報提供にご協力頂きました皆様、本当にありがとうございました。
また職員供出では昨年より若干減りましたが貴重な時間を使って採って頂き感謝しています。採る場所も色々と決めさせてもらいましたが、今年の収穫量の5分の1は職員の手によるものとなりました。
林産班としても多くの方の協力によって成立するドクダミ採りを通して学んだ事はたくさんあり、一人一人の職員の資質を高められたと思います。もちろん林産班の利用者さんたちも本当に良く頑張ってくれました。現在、皆さんに採って頂いたドクダミは乾燥を終え米袋に詰め終えています。皆さんの気持ちがたくさん込められているドクダミ。今年も責任を持って販売していきたいと思います。ご協力ありがとうございました。





2012年6月11日
祝!はーとふるメッセ・オブ・ザ・イヤー2011W受賞!

40年前(昭和49年)の北総周辺。緑の大地遥か遠くに鹿島灘の水平線。茅葺き民家と田圃と畑。何て肥くせえ風景だこと。ここで50名の暮らしが創まった。何で暮らしを立てるか…。「百姓になるしかあんめーよ」。何の迷いもなかった。が、この人たちの多くは船橋のサラリーマンの子。過保護に育てられ土なんかいじったことのない子がほとんど。お借りした3反歩の畑、3畝の田も持て余した。が、野菜は種を蒔けば自力で育ってくれる。わが子を思うちちははは月に一度80㎞離れた船橋からわが子に会いに来た。畑仕事で泥だらけになったわが子が笑顔で迎えた。「そうか○○、こんなになっちまって情けない」。わが子の成長していく姿を切なく見つめながら。出来の善し悪しは別、菜っ葉をちちははは涙を流して買って帰っていくのだ。どんな仕事も同じこと。仕事の終わりは道具の片付け。汚れた”くわ”や”万が”を畑の脇の水路で洗う。最初は「へたくそ」で、洗ったことになっていなかったが、そのうち段々上手になって、泥一つついていない”くわ”。そうやって、どんどん腕を上げて下手な職員より余程染々とした”働くこと生きること”のこの人たちになっていった。全て出来れば、こんな”とこ”には”いない”のだから、読者諸氏はそこから引き算をしてもらいたいが、それは心が鍛えられプライド持った筋金入りの百姓衆の誕生に他ならない。近藤益雄はこの人たちのことを多くの言葉にした教育者であり詩人、そして何よりこの人達と共同生活実践者。彼の詩の中で巻頭”春あさき水にきて”(明治図書出版「近藤益雄」著作集より)が好きだ。あれから40年。今は職員が力をつけて見事な有機農業が売りの北総農耕班。この人たちも年取って白髪頭に禿頭。腰も曲がって年寄りのヨチヨチ歩き。が、その人たちが今も草取りに精出して支えて農耕班は成立している。今年3月3日。千葉県知事肝煎の障害者施設作品品評会(はーとふるメッセ・オブ・ザ・イヤー2011イン幕張)で、その農耕班の切り干し大根が見事優秀賞を射止めた。紙工芸班の和紙干支人形も奨励賞。「いかったなー」「はーいかったぺよ」「えんちょうにうめーもんねだるべーよ」「おら、おかきがいかっぺとおもう」「そんなけちなもん…」
(武井)
春あさき水にきて・・・近藤益雄
畑しごと おえたれば
この子らと
春あさき水に きて
くわを あらいぬ
われも 子らも
水のつめたさを いわず
ていねいに
土を おとしぬ

2012年6月8日
「小さな花」

「小さな花」
新職員として半年。農耕班の皆さんと作業に向かうある日の坂道。土手に咲く小さなタンポポを見て「かわいいね。」「キレイだね。」とYさんやNさんがつぶやいた。そんな利用者の皆さんを見て、自分も自然と笑顔になった。何気なく通っていた道もよく見ると、小さな草花が咲いていることに気づいた。そんな小さな変化を、これからも利用者の皆さんと共有していきたいと改めて感じた日だった。 (吉田)
2012年6月8日
「菜の花寮のベランダで」

「菜の花寮のベランダで」
菜の花寮のベランダ。去年の春まではとてもきれいに咲き誇るソメイヨシノの景色を見る事ができていた場所。今年の春は、ここから見える景色は去年と一変。改修工事の真っ只中です。あのソメイヨシノもなくなってしまいました。そんな中、夕方になると時々、ベランダからその風景を眺めるEさんの姿があります。長年すごしてきた手芸室も、木工室も、陶芸室も解体され、着々と工事が進んでゆくこの情景をEさんはどんな思いで眺めているのだろう。Eさんの思いの隣で、前に進んでゆく工事の景色を、私も一緒に眺めていこうと思った今年の春でした。 (梶浦)
2012年6月8日
「サクラサク」

「サクラサクラ」
今年も北総の周りには白や薄ピンクの桜がきれいに咲きました。
作業場へ行く途中、「サクラすっごくきれい!!」とKさん。四月に入るとお花見をしながら作業に行け、どこかリッチな気分。
桜が咲き始めたある日の事。作業へ行く途中、道で立ち止まっている紙工芸のSさん。ふと見ると桜を指さしていた。その姿はまるで一つ一つ桜の花を数えているようでなんだか微笑ましい光景だった。
桜の花が咲くのは皆楽しみなんだな.。
桜咲き
お酒に団子に
楽しみばかり
あ~幸せだな。 (篠塚)
2012年6月8日
日本の原発全てが停止した。

水上勉の生まれ所在は福井県大飯町字岡田。彼はそのことをこう書いている。「私が生まれ育った若狭の生家は、村で乞食谷と呼ばれた谷の上にあった。人間は暮らせないところだということか、死体を埋めるさんまい谷のとば口にあり、谷の所有者で松宮林左衛門という素封家の薪小屋を借りて住居にしていた。…」(泥の花・河出出版)
読者諸氏は水上勉の小説の何処に惹かれるか。彼は小坊主修行からはじまって、30以上の職業を転々。人間社会の奥底を見つめ続けた作家。名もない庶民の希望と絶望、父母慕情、ただ切ないだけの人生が自分の生きざまと重なりながら語られていく。S36年”雁の寺”で直木賞。東京時代、池袋文芸座で見た”飢餓海峡”。主役の樽見京一郎役は三国連太郎。日本映画の白眉的作品。そんな彼は敗戦間近の昭和20年、生まれ在所の若狭の分教場で代用教員として働く。そのことを彼は”31年目の分教場”として著している。
「…孝ちゃんは、知恵おくれというだけで、他人にめいわくはかけなかった。めいわくといえば、うんこを時々もらすことぐらいだった。こんなことは低学年なら知恵おくれの子でなくてもやることだった。ただ、もう一つ困ったのは、なけなしの配給の画用紙をあたえて、課題の絵をかかせようとすると、孝ちゃんだけは、クレオンでまっ黒かまっ赤にしてしまって、わらっていたことだ。…そんな孝ちゃんが20年に入って急に頭角をあらわすようになった。それは、本校からの指示で、学業は休みにして、午前中から蕗と芋の葉をとって供出しろという命令だった。何貫目の割当てがなされたかはわすれたが、30人の子らを動員して、高野、今寺の野生の蕗を朝から千切って束にし、リヤカーで本校へ運ぶのが日課になった。この蕗は司令部のあった東舞鶴へおくられて兵隊の食料になったときいた。…戦争は敗け戦の兆しをみせていた。だが、それを教師がしゃべるわけにゆかなかった。それで、毎日が暗い気分だった。暗い気分を晴らすのは、一日、山を走りまわって子供らとあそぶことだった。…孝ちゃんは蕗とり上手だった。どういう勘が働くのか、ぼくらがもうそこにはないと思って断念していた谷へ入って、2時間も顔を見せないと思うと、なんと背中いっぱいに背負って汗だくでやってきた。これには参った。孝ちゃんの収穫した蕗は、30人の半分ぐらいあった。自慢するでもなく、にこにこしているだけだった。これが疎開の子らを励ます結果になった。知恵おくれの孝ちゃんでさえ、こんなにとるのだからサボッていたはずかしいという思いが子らに芽生えた。
ある日、ぼくたちは、今寺の部落からさらに北上して、大人でもあまりゆかない深い谷へ入り込んだ。…。夕方になった。点呼してみた。孝ちゃんの顔がなかった。心配になった。日も暮れかかっていた。孝ちゃんの姿をみた者はなかった。そこで手分けして、谷から谷の暗いところや危険な箇所へ声をあげてさがしにいった。「孝ちゃーん、孝ちゃーん。ええかげんにやめてあつまれやァー」。どこからも孝ちゃんは出てこなかった。山は暮れるのが早くて、なすび色になった。ぼくは青ざめた。岩場へ落ちでもしていたら大変だ。知恵おくれの子を、こんなふうに働かせていたことが、急にくやまれて、ぼくは眼先がまっ暗になった。「孝ちゃーん、孝ちゃーん」と子らとともに、それから30分ほどさがして歩いた。ある谷の奥だった。一人の男の子の声がした。「孝ちゃんいたぞォー、孝ちゃんいたぞォー」。ぼくは、子供らをつれてそっちへ走っていった。と、孝ちゃんが、母からつくってもらった大人用の背負い籠に、蕗の束をなんと自分の背丈ほど背負ってくるではないか、にこにこして。「孝ちゃんいたぞォー、孝ちゃんいたぞォー」。呼んでいた子は泣いていた。迎える子らも、声をあげて泣いた。あかね色の空の下で泣く子らは美しかった。…」
筆者は曾て、水上勉の生まれ所在を歩いたことがある。彼の言う”乞食谷”とはいったいどんなところだ。水上ファンとしては長いことそれが気になって仕方なかった。敦賀から小浜線に乗り換え若狭本郷駅下車。大飯町役場は小さな駅舎から程近い。駅から佐分利川沿いに歩いて2㎞。近畿地方は関東とは違う独特の茅葺屋根の民家が昔ながらの集落を形成している。岡田集落は背後に杉山を背負う。前は水田が佐分利川まで続く。出会った姉さ被りのおばさんが「つとむさんの家のあと」を教えてくれた。乞食谷から歩いて10分。勉さんが私財を投じて作った”若州一滴文庫”。館長は勉さんの兄さん。館内で偶然お会いし「兄さんによく似ておられますね」と声を掛けると「私が兄です」…。佐分利川に沿って田舎町に似付かわしくない立派な集合住宅群。大飯原発家族宿舎だ。高度経済成長の日本。60.80年代に次々と作られていった原発。大都会の繁栄を支えるため勉さんの生まれ在所は、”原発銀座”となっていった。勉さんは1970年以後日本の国は自然、風土の荒廃が顕著になり、人間の心の荒廃も進んだと書く。「日本人は、いまやこころを失った。狂人の国である。経済成長だけを呪文のようにとなえているうちに奈落に落ちたのだ」。”泥の花”の中で「私の生まれた若狭にある故障続きの放射能たれ流しと噂されている、高速原子炉ふけんもんじゅから送られる電気…」とある。原発のあり方に強いいらだちを隠さなかった勉さん。
04(平成16)年85才で逝去。
12(平成24)年5月5日、日本の原発全てが停止した。
2012年1月27日
手芸室とお別れ・・・

手芸班のみんなとすごしてきた手芸室。なにもわからない自分を成長させてくれた手芸室。
歴代の利用者、歴代の職員、多くの方がすごされてきた手芸室。
諏訪正子さんと過ごした手芸室。皆の働く姿、ニコニコ笑顔があふれていた手芸室。
お別れのときがくるなんて…。
みんな言葉にはしないけれど、きっと寂しいはず。
みんなの何十年もの思い出がつまった場所だもの。絶対さみしい。そうであってほしい
。そして、いつまでもいい思い出としてみんなの心の中に焼きついていることでしょう。

みんな手芸室とお別れできるかな…。壊されてしまう日…。
手芸室ありがとうございました
(山田)
2012年1月27日
沢山の思い入れがある陶芸の作業場

7年前の4月、新職員で陶芸所属となったが作る事の好きな私にとって陶芸班になった事は嬉しかった事を覚えている。
初めてのロクロ。
毎日毎日苦戦して思うように作れなくて出来ない自分に悔し涙を流したっけ…
初めての一人勤務、不安な思いでいっぱいだったっけ…
初めて出来た湯のみをぐいのみと言われてしまい悔しい思いもしたな…
本当に色々な思いの積み重ねがこの作業場につまっている。
今は陶芸の仕事も覚え慣れもあるが新職員の時はいつもいっぱいいっぱいだったな…と思う。
そんな沢山の思い入れがある陶芸の作業場、私だけでなく他職員、利用者さんの色々な思い出のつまった作業場。
一言では言い表せない思いが沢山つまっている分、壊されてしまうのはとても寂しいが、この7年間今まで本当にありがとうございましたと思い入れのある作業場に言いたいです。
(篠塚)
つくってはこわしてつくってはこわしてなんかいもやっておぼえた。おさらつくったり、うつわつくったりした。ずっとやってたさぎょうばがなくなってさみしい。
(阿部 信一)
2012年1月27日
サクラノキガキラレチャウ・・・

お喋りが大好きなSさんが話し始めると、途端に賑やかになる木工室。
そのお喋りに、自分のことを悪く言っていると勘違いし大声を出して怒るKさん。
この大声に反応して、耳の遠いFさんは「Kうるさい」と注意して、さらに大声で怒るKさん。
職員が3人に注意しているのに「うっせぇぞK」と言い出すCさんと、「Kがうるさいんだよ」と訴えてくるYさん。
元はSさんが原因なのになぜかKさんだけのせいになっている。
その横でIさんが笑いながら一言…
「しょうねぇよ。」
そんな木工班の皆と怒って笑って毎日賑やかに過ごしてきた木工室がなくなる。
四季の移り変わりを一番に教えてくれた木工室前のソメイヨシノ。
この場所で皆と桜を眺めることはもうない。
新しいものを得ると古き良きものがなくなってしまう。
この寂しさは何とも言い難いが、どんな場所でも今日も明日も共に笑い、蕫生?を感じていたい。
(信田)
サクラノシタデオベントウヲタベタ。タノシカッタ。
(川 和久)
レイシャ、ビールノンダ。サミシイ。サクラノキガキラレチャウ。
(渡辺 庸一)